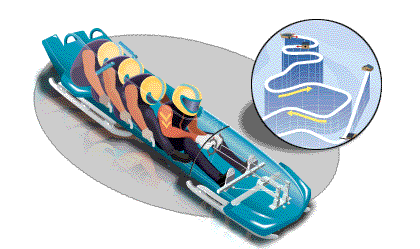ボブスレーは「氷上のF1レース」とも呼ばれる。 そりは、より大きなスリルを求めようとする人々によって開発され、 オリンピックでは1924年の第1回シャモニー・モンブラン大会から正 式競技になっている。オリンピックでは男子だけが行う競技で、2人 乗りと4人乗りの2種目。流線型をした鋼鉄製シャーシのそりに乗り、 ごう音を立てながら延長約1300mの氷の壁を疾走する。1988年の第15 回カルガリー大会では最高時速が143kmにも達した。
競技方法
そりは繊維強化プラスチックで覆われ、前方にハンドル、後方にブレーキを備
えている。前と後にそれぞれ2本のスチール製エッジ(ランナー)があり、
ドライバー(パイロット)が前部のランナーをハンドルで操作しながら滑走する。
スタートダッシュでどれだけスピードをつけられるかが、勝負を大きく左右する。
選手は呼吸を合わせながらそりを押して走り、加速をつけて素早く乗り込む。
押す距離はおよそ50〜60mになる。
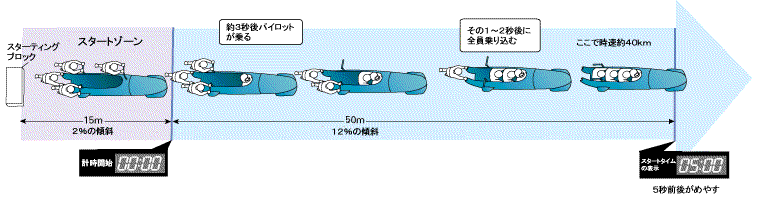
1/1000秒単位で速さを競うボブスレーは、スターとして50mのタイムが結果を左右します。
選手は、シーズンオフになると、車輪をつけたローラーボブスレーで練習をします。
どんな姿勢でも全員そりに乗り込めば記録は認められるが、
1人でも乗り込みに失敗すれば失格
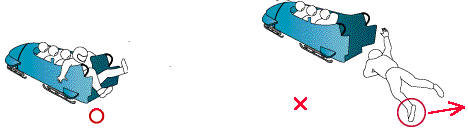
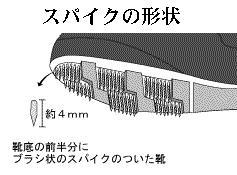
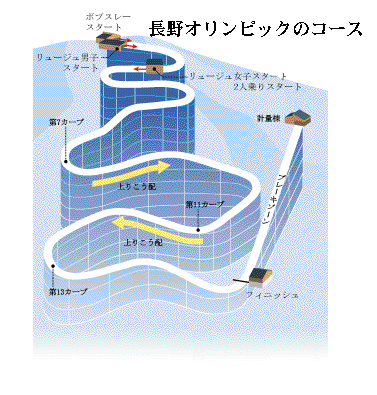
乗り込むタイミングがずれるとスピードのロスにつながる。
乗った後は一番前に座るパイロットの腕の見せどころ。
ハンドルを握って前部のランナーを操り、
氷壁との接触を避けたり、カーブでは滑走ラインを選択する。
後ろでブレーキを操作する選手
(4人乗りでは2、3番目の選手も含む)は、
頭を下げてひたすら小さくなり、空気抵抗を少なくする。
ブレーキは停止用で、コースを傷つけるため、
途中では使用できない。
滑走中、パイロット以外は前を見ず、
押しつぶされるような重圧に耐えている。
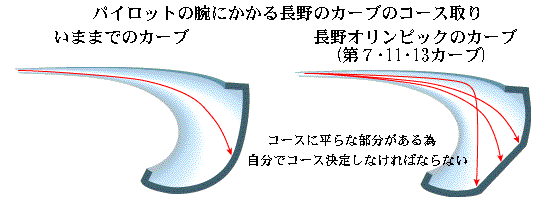 総重量が重いほど加速がついて
総重量が重いほど加速がついて
有利になるため、そりと乗り込む
選手の合計体重は、2人乗りが390kg以下、
4人乗りは630kg以下に制限されている。
選手の体重が軽い時は重りを積み込んでも
よいが、スタートでそりを押す時に余分
力が必要になって不利になる。
総重量はゴールしてから測定する。
また、ランナーの温度が高いほどスピードが出やすくなるため、
基準ランナー(主催者が戸外につり下げたもの)との温度差が4℃以内でなくてはならず、
スタート前に温度を測定する。
競技は2日間で4回滑走し、順位を決める。
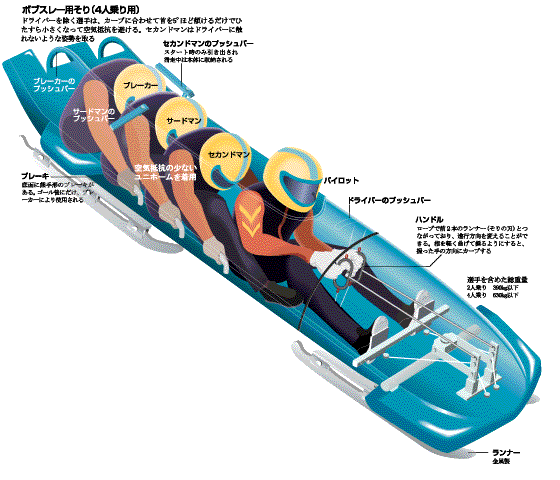
他競技出身の選手も挑戦
滑走中にハンドルを操作するパイロット(前に乗る選手)は経験が重視
されるが、後ろに乗るブレーカーは比較的短期間で強化しやすい。
重量のあるそりを押すパワーや瞬発力が求められるため、陸上など他競
技から転向してくる選手が目立つのが特徴だ。
競技人口の少ない日本では、選手を発掘するため、1992年からコントロ
ールテストを実施している。テストは20m走、60m走、300m走、立ち五段
跳び、ベンチプレス、スクワットの6種目。これらの内容は、陸上の投
てき種目や十種競技をやっていた選手に有利と言える。前回のリレハン
メル大会4人乗りで十種競技出身の選手が出場を果たした。
これが刺激となって陸上選手が積極的に挑戦し、全日本チームに参入している。